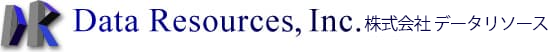SVODはチャーンとの戦い
SVODはチャーンとの戦い
Netflixに続いて、Disney+も加入者数の発表を終了する。理由として、加入者数よりも、エンゲージメントが重要になっていると説明している。SVODはサブスクリプション・モデルからサブスクリプションと広告のハイブリッド・モデルに進んでいる。視聴者が多くても、視聴時間が少なければ、広告収入は増えないので、エンゲージメントが重要になる。
Digital Entertainment Groupによると、SVOD収入に占める広告収入の割合は2024年前半では11.6%であったのが、今年の前半では17.7%に増えている。昨年前期からのSVODにおけるサブスクリプション収入の成長率は8.85%であったのに対して、広告からの収入は78.26%の増加になっている。加入者が増えなくても、エンゲージメントが増えれば収入が増えるので、加入者数は指標にならないとのロジックである。
しかし、SVOD事業者が加入者数の公開を止めている理由はそれ以外にもある。重要な理由として、加入者数の成長が不安定になっていることだ。これは市場が飽和に近づいたのと、チャーンが増えていることが原因している。SVODへの世帯加入率は80%程度になっている。多チャンネルサービスのピークは85%であり、SVODもそれに近づいており、大きな成長は困難になっている。
また、SVODサービスは昨年から平均で25%も値上がりしており、値上げによるチャーンも増えている。1つのサービスに加入し続ける加入者は減っている。殆どのSVOD加入者は同時に加入しているサービスの数を4個程度に調節している。要するに、新しいサービスに加入したら、これまで加入しているサービスの1つを解約する。2019年では2%であったSVODサービスの平均チャーン率は、2025年Q1では3倍近い、5.5%に増えている。解約しても、41%の利用者は1年以内に再加入しており、加入、脱退、再加入を繰り返している。
NetflixとAmazon Prime Videoの2つが、加入し続ける利用者が多く、チャーンが少なかったサービスであった。しかし、Fabric社によるとNetflixのチャーン率は2024年Q1の2%から2015年Q1には3%に増えている。Prime Videoは広告付きにしたことが原因したようで、チャーンは2%から7%にジャンプしている。
チャーンが増えと加入者の成長が不安定になる。例えば、Disney+、WBD(HBO MaxとDiscovery+)、それにPeacockはQ1にアメリカとカナダでそれぞれ、100万人、40万人、500万人の成長をしたが、Q2の加入者増加数は3社共にゼロであった。加入者数が少ないと、株価が落ちる。不安定な加入者数は、不安定な株価をもたらすことになる。加入者の発表を避けるSVODサービスは増えるであろう。
チャーンを減らすために、サービスのバンドルが増えている。利用者はバンドル・サービスに加入することで料金を安くすることが出来、解約の可能性が減る。他のSVODサービスとのバンドルだけでなく、通信サービス、音楽、ゲーム、フィットネス等、様々なバンドルが誕生している。しかし、結局はサブスクリプションを増やすことになり、サブスクリプション疲れ悪化させることになるので、決定的な解決方法ではない。SVOD事業者はチャーンと戦い続けることになり、加入者の発表を避けるSVODサービスは増えていくであろう。