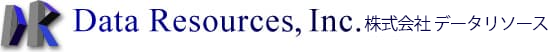- 環境・エネルギー
- 電子部品/半導体
グリーン・スチール革命:よりクリーンで、より強靭で、よりスマートな

鋼は至る所に存在しています——建物、自動車、家電製品、橋梁、さらには風力発電機など。しかし、多くの人々が気づいていないのは、伝統的な鋼の製造が最大の産業由来の二酸化炭素排出源の一つであることです。気候変動への懸念が高まる中、新たな解決策としてグリーン・スチールが浮上しています。
グリーン・スチールはまさにその名の通り——環境に優しい方法で作られた鋼鉄です。鉄鉱石から熱を発生させ酸素を除去するために石炭やコークスに依存する代わりに、グリーン・スチールは再生可能エネルギー由来の電気とグリーン水素を使用します。その結果は?同じ強度の鋼鉄ですが、二酸化炭素排出量が大幅に削減されたものです。
産業と政府が脱炭素化を急ぐ中、グローバルなグリーン・スチール市場は急速に拡大しています。その仕組み、重要性、そして驚異的な成長を後押しする要因を詳しく見ていきましょう。
グリーン・スチールとは何ですか?
グリーン・スチールは、水素ベースの還元や再生可能エネルギーで駆動する電気炉などの低炭素技術を使用して製造されます。従来の鉄鋼製造は石炭に依存していますが、グリーン・スチールはCO₂排出量を大幅に削減します。その結果、強度や機能性を損なうことなく、より持続可能な未来を実現できます。
成長著しい市場
グローバルなグリーン鋼市場は急速に拡大しています。2024年に$7.4億ドルと評価され、2029年までに$19.4億ドルに達すると予測されており、21.4%の年平均成長率(CAGR)で成長しています。この成長は、技術革新だけでなく、重工業における持続可能性への世界的な緊急の取り組みを反映しています。
市場成長の要因は?
1.気候変動対策とESG圧力
政府と企業はネットゼロ排出の達成を誓約しており、鉄鋼メーカーは脱炭素化への圧力を受けています。グリーン・スチールは企業が気候目標を達成し、ESG(環境、社会、ガバナンス)スコアを向上させるのに役立ち、投資誘致の鍵となっています。
2. 建設・自動車業界からの需要
自動車、インフラ、不動産など主要産業は環境に優しい素材への移行を進めています。例えば電気自動車(EV)メーカーは、道路上だけでなくサプライチェーン全体での排出量削減を目指しており、グリーン鋼は戦略的優先事項となっています。
3.政府の支援策とグリーン資金
欧州のグリーン・ディールから米国の気候政策まで、持続可能な製造への公的資金が流入しています。補助金、税制優遇措置、研究開発助成金が、世界中でグリーン・スチールへの移行を加速させています。
イノベーションとテクノロジーが先導する
グリーン鋼の潮流は最先端のテクノロジーによって推進されています。主な手法は以下の通りです:
- 水素ベースの直接還元(H-DRI): 化石燃料を水素に置き換え、鉄鉱石から酸素を除去するプロセス。
- 電気炉(EAF):再生可能エネルギー由来の電気を使用して廃鋼を再利用します。
スタートアップ企業と大手企業は、二酸化炭素回収、クリーンエネルギーの統合、AIを活用した効率化ツールに投資し、グリーン鋼の生産最適化を進めています。
先頭を走る企業は?
グリーン鋼分野のイノベーションを牽引する主要企業には以下の企業が挙げられます:
- SSAB(スウェーデン):水素を使用して化石燃料フリーの鋼を生産した最初の企業の一つ。
- ArcelorMittal: 水素とスマート炉を活用した脱炭素化に大規模投資。
- Tata Steel: インドとヨーロッパで低炭素鋼のイニシアチブを立ち上げ。
- POSCO: 韓国で水素ベースの鋼鉄技術の開発を進めています。
- ThyssenKrupp Steel Europe: 世界最大級のグリーン水素ベースの鋼鉄工場の建設を進めています。
グリーン鋼鉄の未来は?
先行きは興奮に満ちていますが、課題も少なくありません。高い生産コスト、水素の供給制限、インフラの不足が障壁となっています。しかし、政府、民間企業リーダー、技術開発者間の協力が急速にゲームチェンジをもたらしています。
持続可能性を優先する産業が増え、消費者が透明性を求める中、グリーン鋼は例外ではなく、標準となるでしょう。
最終的な考え
グリーン鋼は単なる流行語ではありません。それは低炭素経済への大胆な一歩です。急速なイノベーション、支援的な政策、高まる需要により、地球上で最も二酸化炭素排出量の多い産業の一つを再構築する強力な機会を象徴しています。
鋼の未来は単に強靭なだけではありません。それはスマートで持続可能でグリーンな未来です。
情報源:BCC Research社
お問合せ:BCC Researchへのお問合せはデータリソースoffice@dri.co.jpにご連絡下さい。