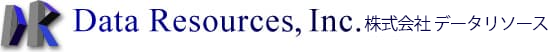なぜNetflixは加入者数の発表をやめたのか
なぜNetflixは加入者数の発表を止めたのか
Netflixは今年のQ1から四半期報告で加入者数を発表することを止めた。加入者数はSVODサービスの成長を見る上は重要な数値であったが、今後は利益とエンゲージメントがフォーカスになる。Netflixが赤字の時代に加入者数の成長を示すことが出来なければ投資家から見放されていたであろう。今のNetflixは違う。2024年における純利益は$871億で、前期から61%の成長があった。加入者数は増えているが、鈍り始めている。
SVOD加入者が減っているのではないが、競合が増えたことでチャーン(解約率)が増え、成長は不安定になっている。2019年まではNetflixの競合と言えば、Amazon Prime VideoとHuluだけであった。現在、主要なSVODサービスとしては、Disney+、Max、Discovery+、Apple TV+、Peacock、Paramount+を含めた9サービスになっている。全サービスに加入することは、金銭的に困難である。サービスに加入し続けるのではなく、定期的に加入と解約を繰り返す人が増えている。これをすれば、同時に加入しているサービス数は4つ程度であっても、1年を通せば、全サービスのコンテンツを見ることが出来る。
SVODサービスの加入状況を調査しているAntenna社はこれをシリアル(連続)チャーンと呼んでおり、解約の内、42%は連続チャーンをしている人によるものだと報告している。連続チャーンをしている人の多くは3ヶ月程度で解約し、別のサービスに加入し、3~6ヶ月後に解約したサービスに再加入する。解約した人の50%は1年以内に再加入しているので、加入者を完全に失う訳では無い。しかし、連続チャーンをする人の行動を予測することは困難である。アメリカのようにSVOD加入者率ですでに高く、成長が少なくなっている地域では、不安定な状況を生み出す。
現時点ではNetflixへの連続チャーンの影響は少ない。チャーンの平均は5%であるのにたいして、Netflixのチャーン2%で、9サービス中ではもっとも低い。次に低いサービスの解約率はDisney+の4%で、Netflixはその半分である。NetflixはSVODサービスとしては古く、ライブラリーも豊富であり、忠誠なファンも多い。連続チャーンをしている人でも、1、2個は加入し続けているサービスがあり、Netflixはその1つである。
しかし、Disney+等の新興勢も開始してから5年経っており、ライブラリーの規模、忠誠なファンも増えている。景気、値上げ等の影響で、Netflixも連続チャーンの大きな影響を受ける可能性は増えている。加入者数が投資家の指標であれば、その時点でNetflixの株価は大きく落ちる。加入者の減少も売上にも影響する。だが、Netflixの広告付きプラン加入者も増え、新たな加入者(再加入含める)の50%近くは広告付きプランを選んでいる。加入者の減少により売上が減っても、エンゲージメント(視聴時間)が増し、広告収入が増えているのであれば、売上の減少は少なく、投資家のパニックを回避することが出来る。これが、加入者数を発表しない理由である。